物を減らし続けた10年間。
それは、震災がきっかけだったのですが少しずつ減らしていくことでわかることがありました。
最初は「環境の改善」だった物を減らすこと
・物を探すのをやめたくて
・もっと簡単に暮らしたくて
・頭がいっぱいになるのをなんとかしたくて
・イライラを防ぎたくて
・安全に暮らしたくて
始めた手放し。
手放すものが本当に多くて、気が遠くなりそうだった10年間。
私が最初に手をつけたのは「台所」。
容易に手放すものを決めることができたからですが、小さなところから始めたのはよかったかもしれません。
減らすことで、暮らしが快適になっていくのは満足度が高く手放しの効果を存分に感じるのでした。
「物を減らすこと」の過渡期
まだ物が多くて、減らすものがあって混沌としていた時、
簡単な片付け箇所が終わり、本や仕事道具などの片付けに着手した時にかなり苦戦。
どうして苦戦するかというと、物と「思い出」や「執着」がセットになっているからだと気づきました。
だから、しばらくボックスの中で「手放しの時」を待ってみたり、一つひとつの物に向き合って「もうさよならしてもいいよね」と判断して。
物を減らす行為は、私自身の暮らしを振り返る行為につながって、
かなり辛さを伴う行為でした。
物には、
・ただの「物」の場合
・「物」に付随する感情がある場合
があって、後者は手放しが困難。
年老いて、片付けをするとなかなか手放せないのは、後者が多いのだろうと感じました。
大変だったけれど、減らしてみて思ったことは
一番、手放しが困難だったのは仕事道具でした。
私は、仕事が大好きでした。
一つひとつに思い入れがあり、手放しがしづらいものばかり。
必要にならなくなっても、なかなか手放しができずにいました。
それで、ずっと保管していたのです。
家の中の手放しを進めていって、ふとある時に、
「もう、手放しても大丈夫な気がする」という時がやってきて。
そこからは、悲しい気持ちを伴うことなく「ありがとう」という気持ちで手放しを行うことができました。
時間はかなりかかりましたが、私としては納得して手放すことができたので手放したものに後悔はありません。
仕事道具の手放しを終えた時に、なんだかひとつの心の重荷がす〜っとなくなっていく感覚がありました。
それは、おそらく他でもない私自身の「こだわり」がなくなった瞬間だったのかもしれません。
物に付随する思いも一緒に整理することができたのだろうと思えました。
モノの手放し=心の整理だったのですね。
そこからは、新しいことへ挑戦したり出会いがあったりなどして、
これまでとは全く違う暮らし方へ変化していきました。
物を手放すというプロセスの中で、自分自身と向かい合えたこと。
それが、今となっては本当によかったと思えています。
一度、物を減らしてからは、
リバウンドすることもなく、時々のメンテナンス(見直し)のみで家を整えられています。
恐れることなく、雑貨類を買うことができるようにもなりました。

私の好きを受け止めて、その好きを暮らしに生かして。
笑顔でいられる暮らしを叶えることができています。
遠回りしたけれど、これでよかったのだと振り返っています。
手放しの方法は、「自分の納得いく方法でやる」
世の中には、手放しを進める投稿や書籍、ブログで溢れています。私もそうです。
けれど、実のところ片付けは「オーダーメイド」その人自身の決断や考え方がとても大切になると思います。
そして、
物が多いも少ないも、その人が笑顔で快適であればいいことで、安易に人へ勧めたり強要することではないなと実感しています。
ブログ内で、手放しのことを書いている時も「自分のこと」として語るのはそういう理由からです。
ですから、時々、
「私のような考え方でミニマリストブロガーを名乗るのは、どうなんだろうな?」と思うこともあります。
けれども、主流の中にほんの少し「異色」が混じっていてもいいじゃないか。
と、少し開き直った気分でこれからもブログを書いていこうかなと思っています。
私なりの「手放し」を書いたKindle本です。
よかったら、お手に取っていただけると嬉しいです。
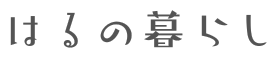











comment